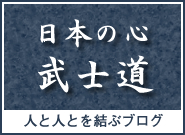全うする
2010年12月9日
責任を取るということは、覚悟を決めることと言い切れるのではないでしょうか。武士の時代のように切腹をして、責任を形にして表すことを良しとしない現代で、責任を取るというのは、その覚悟を決めるのが最重要なことです。お金を使い弁償をする、慰謝料を払う、などいろいろな責任の取り方がありますが。それでも覚悟をした人としていない人では、相手が許せるか許せないか、という一番肝心なところに影響を与えるものです。
覚悟とは、責任を取ろうと決めることです。
和歌
明治天皇御製
9日 世の中の人におくれをとりぬべしすすまぬ時にすすまざりせば
(責任あることは必ず為しとげましょう)
昭建皇太后御歌
10日 人ごとのよきもあしきもこころしてきけばわが身のためとこそなれ
(人々の言葉に注意して、わが身のためと聞きましょう)
日本の心
2010年12月8日
生きていく上で一番辛いことは、役に立たない人間になった時ではないでしょうか。認めてもらいたいという気持ちが満たされるときは、他者から感謝されたり、気持ちをわかってもらえた時でしょう。だから、誰もが誰かの役に立っている時に、自分の存在価値を見出すことができると言っても過言ではないでしょう。
それには努力と反省が欠かせません。努力をして、方向性が合っていたのか? 本当に望まれていることに応えられたのか?など考えて方向を正したりするために必要なことが反省です。努力は「ひたすらに」という言葉が一番ピンとくるかもしれません。
努力を途中でやめてしまう時は、結果が見えないとき、他者に認められないときなどがほとんどではないでしょうか。努力と反省を繰り返していると、自然と謙虚にもなれますね。
和歌
明治天皇御製
7日 さまざまのうきふしを徑へ呉竹のよにすぐれたる人とこそなれ
(努力なくして成功はありません)
昭建皇太后御歌
8日 日にみたび身をかへりみし古の人のこころにならひてしがな
(常に自らを反省した昔の人に習いたいものです)
和
2010年12月6日
和とは、和む(なごむ)という意味を持っています。コミュニケーションを良くするということですね。つまり和歌は和む歌、大和の国の歌、コミュニケーションの手段となる歌という解釈ができます。御製を読んでいると、まさにその通りだと思います。自信を持ち責任を全うすることは、「和」そのものだと思います。素晴らしい人間関係を構築するための手段ともなります。和歌の素晴らしさを子供たちに教えたいですね。
三笠宮様が顧問をなさっているカレッジで今度ある会が催されるそうです。そこで、歌う歌が大正時代の小学唱歌なのですが、それを今の20代の若者は学校で習っていないのです。だから馴染みがなく、歌を口ずさめないという状況です。つまり、学校でガンダムの歌は習っても、小学唱歌は学校で教えてもらえなかったというわけなのです。
それを知った時、歴史や文化が分断されてしまう・・・という恐怖を感じました。国民みんなが母国を大切に思う為には、文化と歴史の継承が必要不可欠ではないでしょうか。
和歌
明治天皇御製
5日 萬代の國のしづめと大空にあふぐは富士のたかねなりけり
(国民の自覚を強くし責任を重んじましょう)
昭建皇太后御歌
6日 むらぎもの心にとひてはぢざらば世の人はいかにありとも
(自信を強く持つことです)
発行 明治神宮社務所
矛盾
2010年12月5日

33回目のテーマは「矛盾」
人生には矛盾がつきものです。
江戸時代は徳川幕府の掟で「喧嘩両成敗」というルールがありました。しかし、藩の掟では、喧嘩を売られてすごすごと引き下がってくるのは意気地なしとされました。でも、喧嘩を売られてその喧嘩を受けたならば、幕府の掟で裁かれて切腹です。喧嘩をしないで戻れば、藩の掟で裁かれて切腹か罷免されて追放です。どうしたらいいの? 疑問です。
こんな理不尽な話はないし矛盾していると、私は当初腹立たしく思っていました。私はこのことをずっと5年間考えた末に答えが見つかりました。今になってこの矛盾が解けて理解できるようになりました。喧嘩を吹っかけられたらもうお終いなのです。喧嘩を売られること事態、平素の心がけが足りないという結果なのです。喧嘩を売る人と売られる人は同じ穴のムジナで同類だと言いたかったのではないか・・・ということです。
私もパワハラに遭った時、上司たちを責めていましたが、私にもターゲットにされる難所があったのだと後になって反省しました。もちろん、その時のずるい上司を好きにはなれませんし、これからも仲よくしたいとも思いません。ずっと見返してやりたいと思っていました。でも、この謎解きができた時、見返すとか悔しいとか腹立たしいという気持ちが、スーッと消えてしまいました。全てが自分との闘いでしかなかったということが理解できたからです。
いじめられない様にするには、信念を持って、自信をもって、自分に誇りをもって、堂々と振る舞うことです。ということは、厳しい冷たい言い方に聞こえるかもしれませんが、詐欺をする人と詐欺をされる人は同じ土俵にいるということになるのです。もちろん詐欺をする加害者が悪い人で、詐欺される被害者は悪くはありません。ただ隙があるというところを言っています。
以前銀行で若い警察官が「オレオレ詐欺にお気をつけください」と言って、キャッシュディスペンサーに並んでいる人にチラシを渡していました。その時、「大変ですね」と警察官を気遣ったのは若い世代の人でした。肝心要な老人は「俺は気をつけてるから詐欺になど遭わない」と冷たく言い放ちチラシの受け取りを拒否していました。
警察官だって好きでチラシをわたしていたのではないと思います。仕事で、上司命令でしょう。拒否されて戸惑いを隠せず、手持無沙汰な表情になっていました。若い警察官に気配りができなかった老人を見ていて、心に木枯らしが吹いているようでした。相手の気持ちや立場を考えずに自分の立場ばかり考えているから、老人相手に詐欺ができてしまうのではないでしょうか。
この老人が詐欺に遭うか遭わないかは分かりません。この老人とは関係ありませんが、ニュースに「振り込みを止めた銀行員を突き飛ばして怪我までさせて振り込んだのに、それがオレオレ詐欺で被害を受けてしまった」と掲載されていました。自分の目先の事しか考えられない、という視点から判断したら、この被害者と詐欺をした加害者は同じ土俵にいますね。
つまり、人間力を高めて、他者の立場や思いを理解することができるような、徳の高い人間になることが土俵を違えることができるということではないでしょうか。江戸時代は平素から喧嘩を売られないような心がけをすること、を求められていたとも言えますね。
武士道が人々の生活の中に存在していた時は、喧嘩を売られない様に注意をして、自分を高めておくことが当たり前であった、と私には理解できたのです。だから、日本は右側通行だったのです。刀は左側にさします。刀にぶつかられたり、触れられたりしたら、間違いなく江戸時代は喧嘩になりました。すごすごと引き下がることは意気地なしですから、こういう時は必ず「待て!!」となったことでしょう。そうなると、どっちに転んでも切腹です。だから、立ち止まっている時、歩いている人が刀にぶつかってこない様に、左側によけて右側を歩かせたのだそうです。
余談ですが今、東京はエスカレーターで左に立ち、右側を歩きます。でも、大阪は大阪万博以来、欧米に合わせて右側に立ち、左側を歩きます。これは日本古来のしきたりからしたら、東京が正しいということになります。車の往来も、日本は左、西欧は右と反対です。
矛盾についての結論は、矛盾しているように見えることでも、良く考えると道理に合っていることもあるということなのですね。
2010年12月5日 05:27 PM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
非礼「蛤の変」
2010年12月4日

非礼「蛤の変」で臨時国会が終わったとニュースに出ていました。皇室に対する非礼問題です。民主党は皇室に対して反感を持っている人の集まりなのでしょうか?それにしては前原さんなどは保守派をうたっていると聞きますが・・・
もし蛤さんが中国の胡錦濤さんを相手に非礼な態度をとってこれだけ問題になっていたら、管総理大臣は今のような態度をとっているでしょうか?相手が皇室だったから? と取れるような態度はいかがなものでしょうか。誰に対しても無礼非礼をしないように心がけるのが人としての振る舞いであり責任です。
礼を守り節度ある振る舞いをしていれば、たとえ相手がどのように立派な、大切な、重要な、目上であっても目下の相手であっても何も問題は起きません。だからこそ、武士道精神が必要であると私は唱えているのです。非礼をするのは、相手を見下し、傲慢になっている証です。自分の役職に酔ってしまい、人間としての正しい行いに対する意識が足りないからであり、根本的な「禽獣との違い」を理解していないことが原因でしょう。
蛤さんがもし、自分の発言が本心でなく、つい口からポロリと出てしまったと言うのであっても、反省すべき点は「謙虚さがない」ということです。また意識して言ったのなら、逃げずに責任を取った方が潔く気持ちがいいですね。
政治家は日本の国民をリードする立場なのですし、国民に生き方のお手本を見せる必要があります。傲慢になるのは政治家を『選ばれた人』の解釈を曲解しているからだと思います。政治家が選ばれた人なのは『私は国民のために私信を捨てて公に生き、国民の手本となる行いをし、国に益をもたらします』と言ったからでしょう。細かい内容は違うにしても、究極的にはこういうことを公約したということです。
それを、自分が立派だから選ばれたと頓珍漢な勘違いをしていたら、四六時中大騒動を起こします。国民に選んで頂いたことに感謝をしていたら、このような恥ずかしい行いで、進退問題を起こしたりはしないはずです。今、蛤さんにとって大切なことは政治家として失脚したくないということではないでしょうか。だから責任を取れないのではないかと思います。もし失脚したくないと思うなら、尚の事、心の底から謙虚になることです。礼をわきまえ、他者を思いやる気持ちを育てることでしょう。それが、我と我が身を守ることになるのですから。
これで分かるように、武士道を身につけて他者に配慮することは、自分の身を守るとになるのです。科学者や物理学者が、研究を深めるにつれて、だんだんと心の在り方のところにたどり着くというのが、それを決定づけていると思います。佐治晴夫先生、佐藤勝彦先生の対談の共著にもありました。
『お金をあげたり、お腹が減っている人にパンをあげたりするのは、「私があなたのためにしてあげる」というのではなくて、この行為によって、私自身が安心するというか、幸せになれる。これが人間の本当の幸せなのかなと。そんなことを考えたりしました。』という佐治先生の言葉です。
蛤さんも、皇室に吐いた暴言は「暴言によって蛤さん自身が周囲からの嘲笑を受けた」ということでした。行いをただし、誰の事も否定せず、避難せず、良い行いを淡々と粛々を続けることが、身を守ることにもつながるということが、ここで改めて実証されました。やはり、今のご時世だからこそ武士道は必要です。
早く学校教育に道徳を取り入れてほしいですね。
武士道精神
素直であること、人を見下さないこと、謙虚であること、和を保ち批判否定をしないこと。そして、傲慢になる己の心を戒め、世のため人のためになることを考え、怠けず働くこと。本当に難しいことですが、清々しく美しい姿です。私も早く武士道精神を身につけて心穏やかに清々しい毎日を送れるよう努力し続けます。
和歌
明治天皇御製
3日 かたしとて思ひたゆまばなにごともなることあらじ人の世の中
(七ころび八起きの決心で励みましょう)
昭建皇太后御歌
4日 人はただすなほならなむ呉竹の世にたちこえむふしはなくとも
(まず第一に心は素直であることが大切です)
発行明治神宮社務所
和歌
2010年12月2日

32回目のテーマは「和歌」
日本の和歌には言霊があるそうです。小さいころ母が、ほつれた糸をほぐしながら和歌を口ずさんでいました。今思い出そうとしても全く思い出せず、失敗!!控えておけばよかったと悔いています。
何かなくしものをした時にうたう和歌もありますが、口ずさむと失せ物が出てきます。母が絡んだ糸をほぐしながらうたっていた時は、そんなことしたって無理とか無駄と思っていました。でも、今は間違いなく和歌には言霊と霊力があると信じます。
日本って素晴らしい国ですね。
日本語って素晴らしいですね。
9歳まで日本語で育てることが、日本の良さを身に着ける条件のようです。そして、戦前までは外国と同じように、日本人はみんな神様を信じていたんでしょうね。神様とは創造主ではなく、神道では先祖のことですから、神社の神様は全て生きていた人を祀っています。
余談ですが、岐阜には天照大神様が生まれたときの胎盤を祀った神社があり、荏名神社といいます。
伊弉冉命が山を下りてきて産気づいて荏名神社のところでお産をしたと言い伝えがあります。
私はこの言い伝えを何故か信じられるんです。
その周辺には春日町という地名もあり、春日大社の名づけの元になっているらしいです。春日町には天之児屋根命が住んでいたそうです。この天之児屋根命は藤原鎌足の祖先で、天の岩戸の前で、天照大神が姿を現してくださるように祝詞をあげた神様です。それで奈良の藤原家の氏神様の名前が「春日大社」となったとか。春日大社の祭神は武甕槌命。大国主命と事代主命に国譲りの交渉をし成功させ、建御名方命との力競べに勝った神様です。その武甕槌命の分霊を鹿島神宮の鹿の背に乗せて大和に運んだと聞いています。
その天照大神様の末裔が天皇家です。ロマンがいっぱいで、夢が膨らみます。その間、色々な戦いがありましたが、神武天皇からで2670年ですから、天照大神様からだと2700年以上も続いているのですね。西暦より長い歴史が脈々と続いていることが素晴らしいと思います。
CW二コル氏の「誇り高き日本人でいたい」という言葉を、私も同感に思います。誇り高くいるためには、生き方を正すことが必要です。相手によって接し方を変えたり、誰も見ていないから手を抜くことは『恥』です。信用信頼のおける人となるように、日々努力が必要です。
明治天皇御製
1日 目に見えぬ 神にむかひてはぢざるは 人の心のまことなりけり
(神様に恥じない心こそ誠の心です)
昭建皇太后御歌
2日 人しれず 思ふこころのよしあしも 照し分くらむ天地のかみ
(心の中も神様はみていらっしゃいます)
発行明治神宮社務所
2010年12月2日 05:29 PM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
明治天皇御製

巌上松
あらし吹く世にも動くな人こころ
いはほに根ざす松のごとくに
たとえ、どのように嵐が吹きすさぶ、はげしい世の中の変動に会っても、あの巌の上に、どっしりと根を張っている松の大木のようにしっかりとした信念を持って、心を動揺させてはなりません。
素晴らしい和歌に出会いました。
これは私が引いたおみくじの大御心です。
まさに今を予測して明治天皇がこの和歌を詠まれたかの如くです。
やはり、おみくじは当たる、と思いました。
外国の占い師には「当たる」と評判とききました。
やはり、周囲がどうであれ、この和歌のように、どんと構えて堂々としていることが必要なのですね。勇気が湧いてきました。
2010年12月2日 09:16 AM | 日記 |
杉原千畝
2010年12月1日

11月29日(日)に半蔵門のPHP研究所にて、『杉原千畝の決断』独り芝居を武士道協会主催で上演されました。協会のHPでは報告しましたが、blogは控えていましたら、投稿が先になってしまい、大変失礼致しました。
宇佐見さんのおっしゃる通りでした。(11月30日に、当ブログにコメントを頂戴しました)
6000人の命は、杉原千畝氏の我が身を捨てた決断により実現されました。水澤心吾さんの感動する演技により、会場は清らかな涙が流れ、老若男女全員が武士道精神が生きる祖先の行為に誇りを持ちました。批判や攻撃はマイナスを生み、思いやりや慈しみは敵の心をも和らげ、解決をもたらすことを証明しているようでした。

祖先の為した武士道精神による行為により、今を生きる人が恩恵を受けている事実を宇佐見さんの投稿で目の当たりにしました。
素敵な投稿をありがとうございました。
改めて、俳優の水澤心吾さんにこの場を借りて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
宇佐見さん、水澤さん、当日ご参加の皆様に感謝します。
武士道協会HP 関連記事⇒http://www.bushido.or.jp/#news_20101128
2010年12月1日 09:23 PM | NPO法人 武士道協会,日記 |
五箇条のご誓文
2010年11月30日

31回目のテーマは「五箇条のご誓文」
昨日、明治神宮を参拝して、もう木々が紅葉していて、散歩にはちょうど良い季節でした。外人の参拝者が多かったです。カラスと一緒に和装の男の子が遊んでいると、外人さんが何人もで写真を撮っていました。男の子は自分を撮られているわからず無邪気に遊んでいました。きっと珍しいのでしょう。
伝統というものが如何に素晴らしいか、外人の興味によって改めて深く感じました。明治神宮という神々しい場所だからでしょうか、道すがら声を掛け合うこともしばしばありました。国と国は揉めていても、そこの国民には親友もいるし、恋人にしている人もいるかもしれません。そう考えると、やはり仲よくするために努力をすることが一番だと思うのです。国同士の仲よくするということを「平和」という言葉で表します。
「平和とは、心に浮き沈みがなく平らけく安らかに落ち着いていて、周囲との和が保ててい状態」という意味を持っています。
平和は左翼と言われる人たちだけが使う言葉ではありません。仲よくするには、平和を維持するには、人間一人一人が努力をしなければならず、ただ何も考えずに過ごしていては「仲よく=平和」の状態を維持することはかなわないのです。「仲よく」するために「武士道」という心の在り方が、今は世界に、つまり、地球上の人類すべてに備わっていると良いと思えるから、武士道を推進しています。武士道は戦争をするための心構えでもなく、生きる上で気持ちを落ち着かせ、冷静な判断をし、他者に迷惑や不快な思いをさせないように生きるための考え方といえましょう。
昨日掲載した教育勅語も、今日掲載する五箇条のご誓文も、世界に通用する素晴らしい教えですね。このような教えが日本にあることを私は誇りに思い、外国籍(外人)の大切な友人に贈ることにしました。日本の政治家の方々に、ぜひいつも胸にご誓文を入れてお仕事をして頂きたいと思います。特に総理大臣に望むところです。
明治神宮で求めてきた教育勅語の裏に書いてありました。
五箇条のご誓文
一.広く会議を興し、万機公論に決すべし。
一.上下心を一にして、盛に経綸を行ふべし。
一.官武一途庶民に至る迄、各其志を遂げ、人心をして倦(うま)ざらしめん事を要す。
一.旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
一.智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし。
我国未曾有の変革を為んとし、朕躬(ちんみ)を以て衆に先じ、天地神明に誓ひ、大に斯国是を定め、万民保全の道を立てんとす。衆亦此旨趣に基き協心努力せよ。
明治元年三月十四日
「五箇条のご誓文」意訳(口語文)
一.広く人材を求めて会議を開き議論を行い、大切なことはすべて公正な意見によって決めましょう。
一.身分の上下を問わず、心を一つにして積極的に国を治め整えましょう。
一.文官や武官はいうまでもなく一般の国民も、それぞれ自分の職責を果たし、各自の志すところを達成できるように、人々に希望を失わせないことが肝要です。
一.これまでの悪い習慣をすてて、何ごとも普遍的な道理に基づいて行いましょう。
一.知識を世界に求めて天皇を中心とするうるわしい国柄や伝統を大切にして、大いに国を発展させましょう。
これにより、わが国は未だかつてない大変革を行おうとするにあたり、私はみずから天地の神々や祖先に誓い、重大な決意のもとに国政に関するこの基本方針を定め、国民の生活を安定させる大道を確立しようとしているところです。皆さんもこの趣旨に基づいて心を合わせて努力してください。
発行:明治神宮社務所 平成22年10月
2010年11月30日 10:48 AM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |